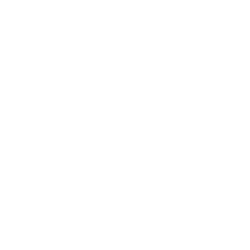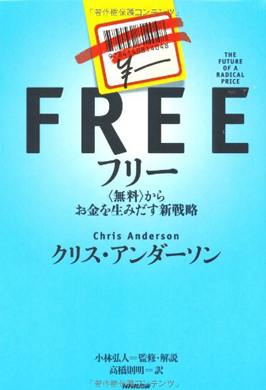 日本放送出版協会 ISBN:978-4140814048 クリス・アンダーソン著/小林弘人 監修/高橋則明 訳(C)日本放送出版協会
日本放送出版協会 ISBN:978-4140814048 クリス・アンダーソン著/小林弘人 監修/高橋則明 訳(C)日本放送出版協会
私たちの周りには“無料”のものがあふれている。何故だろう。本書は私たちを取り巻くこの不思議な“無料”という値付けをめぐる事象について米国のデジタルカルチャー雑誌『Wired』の元編集長クリス・アンダーソンが解説したものである。
単刀直入に結論から書いてしまえば、彼の口からは“無料”に関する極端な肯定も極端な否定も出てこない。その代わりに提示されるのは、一見すると同じように見えるさまざまな“無料”と呼ばれるものの詳細な分類だ。「本当に無料のもの」「無料に見えるが別の形で何かの支払いをしているもの」「無料ではないが無料と見なしても良いぐらいのわずかなコストしか発生しないもの」それらを全部含めて“無料”という吸引力を持った経済の世界が形成される。その中には教会での無料奉仕活動もある。スポンサーがコストを支払い、視聴者が広告を見る対価として番組を無料で見られるテレビもある。詐欺師があとから巨額の金を騙し取るためのうまい話なども含まれる。著者がこの本で考える“無料”の概念は、私たちが日常的に目にする“無料”よりずっと広く体系的だ。この本で最初に書き起こされるエピソードはグーグルでもテレビ放送でもなく、19世紀末に考案された家庭用フルーツゼリーの素『Jell-O(ジェロ)』が普及していった過程の話なのだ。
最初は売り上げ不振だったこの味付き粉末ゼラチンが、米国のセールスマンのネットワークによって無料のレシピを配ることで成長するところから話は始まるのだ。もちろん、それはただのビジネス成功談ではなく、そこから粉末ゼラチンという物理的な質量を持つ「もの」と、粉末ゼラチンを使ったおいしそうなデザート用ゼリーの作り方という「情報」の二つを抜き出して、なぜ粉末ゼラチンは有料で、レシピが無料なのかという根本的な話に読者を誘っていく。
著者の視点の面白いところは、そもそも無償の行動というのは今のような“無料”のサービスが生まれる遙か以前から人間社会には当然のものとして存在する、という部分にまで踏み込んだ視点を持っている点だ。 人間社会に貨幣経済が行き渡る前から人間の社会は“無料”の行動によって支えられてきた。家族間の行動は基本的に“無料”でやりとりをするのが当然であったし、社会や部族の間の交流でも“無料”は珍しいことではなかった。むしろ“無料”という概念は、貨幣経済が世の中を埋め尽くそうとする運動の中で「全てのものには価格がつけられなければならない」という前提があって初めて目に見える形で生まれてきたものだ。
本書で詳細に解説されるさまざまな“無料”ビジネスのからくりを、どうして現代社会に生きる私たちが知らなければならないのだろう。 私たちはすでに身の回りを“無料”のサービスに囲まれて暮らしている。
考えてもみて欲しい。私たちは日常生活を送るにせよ、社会活動に関わるにせよ、何かしら“無料”のものと関わっている。フェイスブックで情報を共有し、グーグルで検索をし、テレビで情報を得て、何か重要な発表をする時にはテレビの影響力を考慮しようとする。それは“無料”だから危険なのだろうか。危険だけれどもすでに偏在しているが故に目をつぶらなくてはならない毒のようなものなのだろうか。
著者の解説を読む限りではそういう話ではないようだ。これは“無料”に限らず、どのような話にも共通することなのだが、妥当な値引きを拒む必要は無いし、妥当な根拠が見当たらない値引きには警戒をするべきだ。それがたとえものの値段をゼロ以下にまで引き下げていたとしても、基本的な考え方は同じであろう。
ゆえに著者は“無料”の是非を話題にはせずに、つねに“無料”であることの源泉を詳らかにし、分類して解説するのである。
著者は“無料”を怖がりすぎるのも、“無料”を使い潰すのも肯定はしていない。”無料”をむやみやたらに得体の知れないものだと怖がる必要は無いのだ。自分がその代わりに何を支払っているのかを自覚していれば。“無料”そのものは料金が発生しない状態のことではあるものの、筆者の視点は貨幣経済だけではなく、貨幣以外のさまざまな要素のやりとりの一形態として話が進められている。当然、料金が発生していないサービスの中にはお金以外の何かを支払っている場合も含まれる。たとえばそれは労力、時間、自己表現の機会、人間関係などである。私たちが社会に対して支払えるものはお金ばかりだとは限らないのだ。ここは本書がただお金儲けの仕組みの解説をするに留まらない醍醐味の部分だろうと思う。
その一方で正反対の立場、つまり“無料”を使い潰そうとする人たちも世の中には存在する。”無料”で使えるサービスがあれば、つねに一定の割合でフリーライダーは出てきてしまうのだ。フリーライダーというのはいわゆるサービスのただ乗りを意図的に繰り返す人たちのことで、彼らは“無料”のサービスを無料であるが故に自分の必要以上に使い倒す。このように無料だからと言って無尽にそのサービスを受け取り、フリーライダーに徹する事が最も有利な選択だとの考えにも筆者は否定的だ。正当な対価を支払わずに行ったフリーライダー的な行為は回り回ってその人から相応の対価を奪い去るのだ。もちろん、それは真っ先にその“無料”サービスが成り立たなくなって食い潰される、つまり“場”が成立しなくなるという形で跳ね返ってくるが、そこで逃げ切りを狙う(これこそがフリーライダーの真の目的である)行為も視点を貨幣経済に限定しなければ回り回って金銭とは違う形でその人を追い込んでいくのは当然のことである。
このむやみやたらと“無料”を怖がる態度とフリーライダーに徹する態度は本書の中では一見相反するようにみえて、実はよく似た行動なのだということに気付かされる。両方とも、どうして“無料”なのかという点を見ようとしない闇雲な行動なのだ。潔癖にはねつけるのも、“無料”にどっぷり浸かるのも。
だから私たちは私たちを取り囲む“無料”を見なくてはならない。社会活動をする上で友人と連絡を取るのにフェイスブックやツイッターを避ける必要は無い。ただし社会正義を追求するのに、その問題に関わる大企業をスポンサーにするのはまずいだろう。いくらコストをゼロにできたとしてもだ。
素人には雲をつかむような利害関係をいくつかの類型に分類して紹介してくれている。全てを解き明かしている訳ではない。事典ではないのだから。しかしどのような仕組みがあるのかは理解できる。消費者の目からはブラックボックスに見える業界関係者の都合も、少なくともブラックボックスがブラックボックスであるように見えるぐらいには手助けをしてくれる。分かっている事を確認する点においても、これまでこのテーマを考えてこなかった人に思考の手がかりを与えてくれるという点においても本書は非常に重宝である。
現代のネット社会で突然降って湧いたかのように見える“無料”に戸惑いを覚える人も世の中には数多く存在すると思うのだが、本書はそのような人だけでなく、むしろ新奇な“無料”に目を奪われ、コンピューター世代のはるか前から存在していた“無料”に慣れっこになってしまった人たちにこそ役に立つ本なのではないかと私は思う。 “無料”を使ってビジネスモデルを考える経営者よりは、消費者として“無料”に接する普通の人たちにこそ、私はこの本をお薦めしたい。
(執筆:アムネスティ書評委員会 T. N)
本を購入する
▽ 下記のリンクよりご購入ください。
フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略