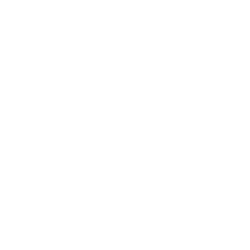ブリギッテ・ハーマン著、 中村康之訳/朝日新聞社/978-4-02-261488-9/(C)朝日新聞社
ブリギッテ・ハーマン著、 中村康之訳/朝日新聞社/978-4-02-261488-9/(C)朝日新聞社
21世紀の現代でも「女子力」なるものがクローズアップされ、たとえビジネスやスポーツで活躍している女性であっても、家事ができるか、結婚しているかどうかが注目される。男性に対してそのようなことはあるだろうか? 女性に対する意識は、いまだ19世紀とさほど変わりがないのかも知れない。
19世紀後半のハプスブルグ帝国の皇后であったエリザベート。しかし、皇后でありながら、彼女は「一個人」としての権利を主張し、「女性」として求められる役割を何ひとつ果たそうとせず、宮廷でのしきたりを嫌っていた。つまり、皇帝である夫を支えることをせず、公式行事にもほとんど出席せず、家族の団欒も持たず、ひたすら旅に出ることで、宮廷と夫から逃れ、夫に献身的につくす「妻」、一家の「母」、帝国の「皇后」という役割を拒否した。彼女は、20世紀になりようやく女性達が追い求め始め、そして21世紀の現代でも追い求め続けている「個」を貫く生き方に目覚めていたのである。
本書が原作と言われるミュージカル「エリザベート」は大ヒット作品として有名である。作品自体の素晴らしさもあるが、「誰にも束縛されず自由に生きるの」「私の人生は私のもの」と歌うエリザベートの生き方に共感し、羨望を覚える女性が多いからではないだろうか。現代の女性は、彼女が生きた19世紀から比べると、はるかに解放され、自由に生きることのできるにも関わらずである。それはつまり、まだ女性の(男性もまた然りではあるが)生き方に役割が求められ、窮屈なものであるということなのだ。
ストーリーはミステリーとして一応の解決を見るが、そこはおそらく付け足しでしかない。読者はそれよりも、作中に表れるさまざまな言葉を心待ちにしている。読者は自分たちの立場をどこかに見出すというより、議論の中にちりばめられた刺激的な言葉を受け取りながらこの作品のインパクトを感じていく。
民衆が苦しい生活を強いられている中、皇后が自身の役割を拒絶し、ともするとわがままで身勝手と捉えられてしまう生活をしていたことへの是非は問われるところではある。しかし、本書を通して、エリザベートの生き様に触れ、女性の生き方を、そしてまた「個」の追求というものを、改めて考えてみるのもよいのではないかと思う。
(執筆:アムネスティ書評委員会 A.S)
本を購入する
▽ 下記のリンクよりご購入ください。
エリザベート (上) 美しき皇妃の伝説 (朝日文庫)