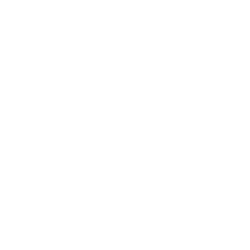出版社:文藝春秋/ISBN:978-4-16344-080-4/(C)文藝春秋
出版社:文藝春秋/ISBN:978-4-16344-080-4/(C)文藝春秋
「何でもヅカヅかいえる人。しかしもう一つぴったりせず。未知数だけに興味がある」。百合子の初対面の印象を、芳子はこう書いた。
二人の出会いは、1924年4月。芳子は27歳、百合子は25歳。天才作家として17歳でデビューしてから、百合子は創作を続け、芳子はロシア文学の研究に励んでいた。二人はたちまち惹かれあい、閑静な住まいを見つけ、共に暮らし始める。百合子は旺盛に執筆活動を行い、芳子もロシア語の翻訳に没頭する。
世間の人々は二人を同性愛夫婦と呼んでからかった。自分の気持に正直に生きなくて何が人生だ。芳子はそういう生き方だ。何という名であろうとも、貴女の愛で、貴女という心の城を持って生きる。百合子は誓う。だが芳子との生活に肉体的満足はない。百合子の官能の高まりは、宙ぶらりんのままだ。
翻訳を生業とするためには、現地で勉強しなければと、芳子はソビエト行きを決意する。
絵本のようにふんわりと雪の積もるモスクワに、二人は降り立った。ロシア革命から十年が過ぎていた。昼間はロシア語の勉強をして、夜は芝居を見て回る。百合子の関心は、次第に外へと向かっていく。ソビエトにいながらその思想を学ぼうとしない芳子に、百合子は苛立つ。
だが芳子は、革命で英雄となった男たちが古い妻を捨て、若い妻を娶るのを見逃さない。捨てられた妻たちは、深い失意の中にいた。ソビエト社会を理想化する百合子との溝は広がる。
3年ぶりに帰国すると、ソビエトを目撃した女流作家として、百合子は注目の的になる。芳子の留守中に百合子は家を飛び出し、恋する男のもとへ向かう。この男こそ、後の日本共産党議長・宮本顕治―。プロレタリア作家・宮本百合子の誕生である。芳子はロシア文学者・湯浅芳子として、広く知られるようになった。
著者はこう問いかける。もしも二人が、互いの愛の意味をもっと信じ合うことができたなら。フェミニズムが市民権を得る半世紀後に生きていたなら、と。二人の日記や書簡は、少しも色あせることがない。孤高の魂のふれあいを綴った稀有な愛の記録である。
(執筆:書評委員会メンバー K.T)
本を購入する
▽ 下記のリンクよりご購入ください。
百合子、ダスヴィダーニヤ―湯浅芳子の青春