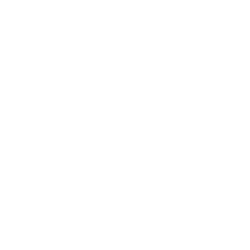光市の母子殺害事件に関して社会が望むのは、「罪の認識」「謝罪」そして「処刑」の三点セット。つまり私たちが理想とする人間になって死んでくれということなのだろう。報道は誰がいつ何をやったかのかばかりで、その人がなぜその犯罪を犯してしまったのかは考えようとしない。
殺すことでホッとするのは、「死刑」を声高に叫ぶ大衆なのだろう。そこには、犯罪は社会が生み出すものという認識がない。変な奴が突然沸いてきて、だからそれを目の前から抹殺すればすべてが解決するかのようだ。まさに文化人類学が言うところの「いけにえ」であり「人柱」である。結果として、犯罪を作り出す社会が温存される。
先日、2001年に広島で自分の母親と娘二人を殺したとされた男性に無罪判決が出た。冤罪にならずに良かったと思う私の気持ちとは裏腹に、テレビでは「えっ?」という空気が漂っていた。なかには「3人も殺したんですよ」と犯人呼ばわりするコメントもあった。
そう、冤罪かどうかなんて関係がないのだ。
犯罪が起きたらいけにえ、人柱が必要であり、それが冤罪だろうが真犯人だろうが、捕まえさえすれば社会は安心する。かつての狭山差別事件はその象徴である。
元プロボクサーの袴田巌さん(66年、味噌製造会社の一家惨殺放火事件の容疑者として逮捕)が獄中から無実を叫んでいる姿を見ると、胸がかきむしられる。死刑制度の現実を少しでも知れば、拘束された中で無実を叫び続けることがどれほど困難な、人間の最後の尊厳をかけた叫びであるかが分かる。だのに、死刑判決で人一人を殺そうとするとき、とことん事実と向き合って真実を究明しようとする司法の意思が感じられない。
袴田さんは人身御供だからだ。大衆の不安を鎮めるために提供された人柱だからだ。
人を殺しても、必ず死刑が求刑されるわけではない。つまり死刑は、殺人という罪を命をもって償わせるためにあるのではなく、何か別の目的があって存続させられているのだ。刑法を見ると、内乱罪や外国のスパイ行為など反政府的行為も死刑の対照となっている。とどのつまり、反権力を抹殺する手段として、人を殺していなくても死刑にできるよう、死刑制度が権力によって温存されていると考えざるを得ない。そのための人身御供が冤罪をも含めた死刑囚たちなのだろう。
袴田巌さんは、そのために死刑台の前に立たされているのだ。私はまだまだ不勉強だ。しかし、少しでも「死刑」の現実を知れば、声を大にして死刑反対を叫ばざるを得ない。
殺すな! 殺させるな! 殺されるな!
(この原稿は、「週刊新社会」2007年12月18日に掲載のものです。辛淑玉さん公式ホームページ)