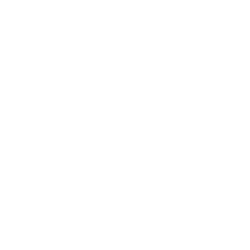江戸期、明治期の死刑からの死刑考察
江戸期の刑罰
「公事方御定書」とは、長い戦乱の時代を経、徳川政権下で時代も落ち着きを取り戻したので、八代将軍の徳川吉宗が、極端に残虐な私刑の類は廃し、罰則を合理的なものに整理せんものと考えて、評定所(ひょうじょうしょ)に編さんさせた全十一巻に及ぶ法典である。
上巻は八十一箇条の法令集。下巻は百三箇条の刑法、訴訟法関連の判例、法令から成る。いわゆる「御定書百箇条」とは、この下巻のみをさして言うことが多い。
江戸時代の刑法は、時代が近いこともあって、その内容が比較的正確に知られている。定められた刑罰は、大別して「死刑」、「肉刑」、「追放刑」、「奴隷刑」、「自由刑」、「労役刑」、「財産刑」の七種に大別される。 「肉刑」とは鞭打ちや入れ墨によるマーキング、「追放刑」は流刑や江戸払い、「奴隷刑」は相応の権力者に終生使役人として下げ渡し、生殺与奪の権限を与えるというもの、「自由刑」は鎖付けなどによって生活の自由を奪い、「労役刑」は今日で言う懲役、「財産刑」は財産を没収するものである。
このうちの死刑は、軽いものから重いものに向け、「下手人」、「死罪」、「斬罪」、「火罪」、「獄門」、「磔」、「鋸挽き」、そして別格として「切腹」の八種に大別された。切腹を別とし、「徳川律法の七種」と呼ぶこともある。あるいは「斬罪」を別には数えず、六種とすることもある。
当世流のこうした分類発想は今日では解りにくいから、殺害の手段を物理的に分類すると、「断首」、「火焙り」、「磔」、「鋸挽き」の四種となる。順に、刀による斬首殺、火による焼殺、槍による刺殺、鋸による頚部の挽き殺し、と理解することができる。
この中の「断首」が、方法の細かな相違から、「下手人」、「死罪」、「斬罪」の三種に分類できるということであり、殺すだけでは不足なので、さらに屈辱を与えるため、「引き廻し」、「獄門」、「試し斬り」という加虐が、追加の罰則として用意されていた、という理解がよい。
「引き廻し」、「獄門」というものは、死刑囚の顔を一般大衆に晒すというものであるが、生前の晒しが「引き廻し」、刑死後の晒しが「獄門」ということである。「試し斬り」とは、刀の切れ味を、刑死者の体を使って実地に試すというもの。
「公事方御定書」の定める行刑の主眼目はあきらかに「死刑」で、他は付け足しのようなところがある。死刑のランク付けの精神は、あっさり殺すか、それとも死の苦痛を長引かせるかの相違で、これに加えてさらに精神的屈辱を与えるとか、反映刑と称し、罪人の犯した罪を、戻す罰のうちに反映するという考え方等によって、ヴァリエーションが八種となっている。
この中で、屈辱の度合いが最も少ないものが「切腹」であるが、これは社会的高位者である武士に、体面を保たせるための自殺であるから性格がまったく異なる。死刑のうちでは「下手人」が最も罪が軽く、「鋸挽き」に向かうほどに重罪となる。以下で、このそれぞれの内容を解説してみる。
-
「下手人」、「死罪」は、ともに比較的罪状の軽い庶民に対する死刑で、あっさりと殺すものである。双方ともに、牢屋敷において執行した。
囚人を縛し、横方向に長く掘った血溜り穴の、手前に敷いた筵(むしろ)にすわらせる。これを「首の座」と称し、処刑場を「斬り場」、もしくは「土壇場」といった。現在の「土壇場」という言葉は、ここから来ている。
「下手人」、「死罪」の場合は囚人に目隠しをし、両肩と背後という具合に、非人が三人がかりで囚人を押さえ、血溜り穴の上に首を突き出させる。そして背後の者が囚人の両足親指を後方に引くと、この時囚人の首が前方に突き出すように伸びるから、首斬り役人がこの一瞬をとらえて首を刎ねた。この時、頚部切断面から噴き出る血は、およそ一升瓶一杯半といわれる。
斬り落とした囚人の首は、獄門に晒すものはきれいに洗って首俵に入れ、保存する。「下手人」の遺体は遺族に下げ渡されるが、「死罪」の遺体は下げ渡されず、刀の試し切りに供される。「死罪」に処した囚人の方が、罪が重いからである。
-
遺体を、刀の試し切りに供するという刑罰は、日本に独特で、古くから武士の習慣としてある。これは「様(ためし)」と称し、キリスタンとして処刑した外国人宣教師に対しても、これは行われた。最近では太平洋戦争中、上に述べたような方法で斬首処刑した外国人捕虜の遺体に、日本軍将校がこの試し斬りを行ったとして、東京裁判で問題となった。
「試し斬り」は、江戸期にはすでにさまざまな作法が完成しており、これを行う者は山田浅右衛門を代々名乗る、世襲の専門職に限られた。試し斬りで斬れ味を試すよう依頼される刀剣は、白鞘に収めて渡され、上に「何様御用」と書いた紙が貼り付けられた。試し斬りの場所は土壇場の脇に、土を二尺ほど積み、上をまな板のように平らにならして作られた。
囚人が殺されたら、非人たちが遺体を運んでここに置き、上体と下半身それぞれを、非人の一人ずつが持つ。浅右衛門は、この遺体のたいてい腹部を一刀両断にした。この瞬間、非人たちは遺体をおのおのの方向に少し引き、切断されていることを示す。
切れ味の良否は、報告書として紙に書いて提出される。下手人だけでなく、武士、僧侶、入墨者、女性、癩病者、混瘡(こんそう)病者、穢多、非人の刑死者に対しては、行わないのが習いであった。山田浅右衛門は腕がたつので、次第に処刑の首斬りも依頼されるようになっていく。
-
「斬罪」は、「下手人」、「死罪」の場合と、処刑法や手順はまったく同じであるが、囚人が武士身分の者である場合を言う。違いとしては、土壇場で首を刎ねる際、この者の場合は目隠しをせず、江戸の場合は浅草、もしくは品川の刑場で首を斬った。そしてこの死体は、試し切りには供しなかった。
「切腹」は別とし、「斬首」以上の「火罪」、「磔」、「鋸挽き」というような重罪人になると、必ず「引き廻し」という付加罰が付いた。これは処刑前の囚人を裸馬に乗せ、市中を引き廻して、公衆に見物させるという趣向のものである。見せしめの意味あいもあるが、囚人に対し、死の苦痛だけでなく、晒しの恥辱も加えようと意図するものである。
-
「引き廻し」の行列は、囚人一人について五、六人の付き人という割合で、なかなか仰々しいものであった。先頭に六尺棒を持った非人が五人、その後方に幟(のぼり)持ち、捨て札持ち、朱槍持ちという順で続く。
幟は幅五尺五寸、縦八尺五寸で、大判の錦の内紙紙を三十六枚貼り合わせて作る決まりになっていて、これに囚人の姓名、生国、罪状、刑罰がぎっしりと記された。捨て札は幅六尺、高さ一尺で、これは処刑場に立てる。
囚人は通常白衣を着せられるが、希望があれば、囚人の最も気に入ったものを着ることが許された。そうして後ろ手に縛られ、首には紙こよりの白数珠をかけられ、裸馬に乗せられた。囚人の数が増えれば、付く人数も同じ割合で増したから、複数の囚人の引き廻しともなると、大行列となった。
行列は牢屋敷裏門から出て、小塚原か鈴が森、板橋などにある刑場に向かうが、罪状によって距離に長短があり、軽いものなら日本橋から江戸橋の通りを引き廻し、重い者なら江戸城を一周させた。軽い者は捨て札がひとつ、重い者は多くの捨て札を沿道に立てさせた。
引き廻しの見物人は常に多く、祭のようになった。引き廻しの日、沿道にあたった店々は、たいてい戸を閉め、簾をかけた。これは囚人が沿道の店に目をとめ、店が商う何かを食べたいと言えば、問答無用に与えることが習慣になっていたからで、経営者たちはこれを気味悪く感じて、みなが店を閉めた。しかし囚人の内には冥土の土産に市中の見物ができると、引き廻しを喜ぶ者もいた。
-
「火罪」は、前述のいわゆる反映刑で、鎌倉時代の貞永式目の時代、不義密通の罪を犯した男女の性器に加えた「宮刑」に似ている。江戸時代にはこの残酷を廃し、ただ死刑としたが、放火の罪を為した者は、炎によって焼殺した。
火付けは重罪と見なされ、必ず引き廻しが付いた。行列が、見物人の群がって待つ鈴が森などの刑場に着くと、六人の非人が囚人を馬から抱え降ろし、柱に縛りつける。死刑囚の周囲には、囚人の体が隠れるほどに燃料の茅(かや)を積み重ねる。終わった時点から同心が立ち会い、罪人当人に間違いないことを確かめる。
別の茅に点火し、これが燃えてから、風上側の茅に火を付ける。筵であおぎ、火勢を強める。茅の束は七百束もあり、これがすべて燃やされる。終わると燃え残りを取り払い、黒焦げになった死体を検分する。茅の束を持って二人の非人が進み出、これに火を移して一人が鼻を焼き、もう一人は男囚の場合陰嚢を、女囚の場合は乳房を焼いて、留めを刺すことが決まりとなっていた。しかし火罪の場合、囚人がなかなか絶命しないで苦しむから、点火する前にあらかじめ絞殺しておくことが次第に慣例となった。
火罪の遺体は埋葬されず、見せしめのために三日二夜、黒焦げのままで晒されたのち、刑場のすみに投げ棄てられた。このため、以降野犬が死体に群がったり、真黒くなるほどに野鳥が群がって肉をついばんだりの光景が展開した。
-
「獄門」は、刎ねた首を、見せしめとしてしばらく市民に晒すというもので、これは「引き廻し」と同じく、「獄門」という処刑方法が別個に存在したわけではなく、「下手人」、「死罪」、「斬罪」、そして後述の「磔」の者でも、見せしめの必要があると判定された者は、死刑執行後にこの罰を付加された。
「獄門」という名称は、古くから牢獄の門に死刑囚の首をかけ、晒すのが習わしであったため、そういう呼び名が生じて定着し、江戸期にいたっていたといわれる。
「獄門」もまた、江戸期にいたるとうるさい作法が細部まで完成しており、斬首した首は首俵に入れ、上部に青竹を通して二人で担ぎ、行列を作って小塚原か鈴が森の晒し場まで運んだ。遠方まで運ぶ場合は、塩漬けか酒漬けにした。
晒し場には、地上高三尺五寸、地下二尺五寸の獄門台が処刑のたびに新調され、中央には「逆さ釘」が出されていて、罪人の首はこの釘に挿して固定された。さらに左右に粘土が置かれ、安定させられることが多かった。晒し台の寸法は厳しく定められていて、台の長さは一人用は四尺、二人用は六尺、三人用は八尺と決まっていた。幅は一尺で、木材の厚さは二寸であった。
この時、引き廻し刑に処せられた者の氏名、罪状などを書いた幟り旗を左側に立てかけておく。右側には杭を二本打って綱を渡し、これに捕り物道具二本と、槍を二本、民への威圧の意味あいで立てかけておき、近くには、罪状を書いた立て札も立てる決まりとなっていた。
やや離れた場所には筵覆いの小屋が建てられ、九名の番人が交替で見張りにあたった。三日間晒し終わると首は捨て、飾り道具も片づけたが、罪名を書いた立て札だけはさらに四日間立てたままにしておき、通行人に読ませた。
小塚原の獄門台の前には水田があったが、これは「睨み田」と呼ばれ、民に恐れられ、耕す者が出なかった。獄門台の晒し首は、みなこの田を睨むことになったからである。
-
「磔」の刑も火罪に似ていて、引き廻しののち、大勢の見物人が待つ刑場に着くと、六人の非人が囚人を馬から降ろし、柱に縛りつける。この柱の形状が、男囚と女囚とでは異なる。男のものは片仮名の「キ」の字の形、女のものは「十字架」型だった。
罪人を縛りつけると、槍で突きやすくするため、衣服の左右を切り裂いて脇腹を露出させる。残った布は中央部分で二、三個所縛り、脇腹を隠さないようにする。そうした準備がすんだら、手伝い人足十数人で柱を起こして穴に落とし込み、立てる。
磔台の下に、下働きの非人二人がそれぞれ槍を持って立ち、左右に分かれると、槍を前方上方に突き出して、囚人の目の前でいったん交差させる。これを「見せ槍」と称した。
続いて掛け声とともに、一人が脇腹から対角線上の肩を目ざし、強く槍を突き入れる。肩から槍の先が一尺ばかり飛び出すことを正式作法とした。それからひとひねりして槍を抜く。すると滝のように血が傷口から流れ出す。反対側に立つ者も、同様にして逆側から対角線上の肩を目指して槍を突き入れる。刃先が骨を貫き、槍が動かなくなることもあった。
こうして二、三十回も突き続けたのち、最後には囚人の喉を突いて留めを刺す。脇腹には大きな穴が開くが、囚人はたいてい最初の二、三突きで絶命する。
遺体は、磔にしたまま三日二夜晒しておくが、三日後には降ろし、穴に投げ込む
-
「鋸挽き」の罪人は、やはり江戸市中引き廻しのあと、晒し場に定められていた日本橋南詰めの広場に到着すると、ここに三尺四方、深さ二尺五寸の穴があらかじめ掘られてあって、この中に「晒し箱」と呼ばれる木箱が入っていた。箱の中央には太い杭が立てられていて、底には筵が敷いてある。囚人はこの上にすわらされ、杭に縛りつけられた。
終わると囚人の首を二枚の首枷板ではさみ、これは箱の蓋ともなっているから、囚人は板の上に頭部だけが出る格好になる。そうしておいて、蓋の上に砂を詰めた俵を六個、重しとして置く。箱の周囲には土をかけ、傍らには三尺もある鋸を置く。さらにもう一本、竹でできた鋸も立てかけ、こちらには囚人の肩を斬って出した血を塗っておく。すでに誰かが囚人の首を少し挽いたように見せるためである。
囚人の罪状と、「首を挽きたい者は挽いてよい」と書いた立て札をそばに立て、このまま二日間放置した。竹の鋸は、金属の鋸に較べて切れ味が鈍いから、これで首を挽かれると苦痛は尋常ではない。しかし泰平の江戸期に入ると、江戸一の盛り場のことで見物人は多いが、鋸を挽こうという猛者はまったく出なかったから、実質上この刑は、晒しの効果だけとなった。二日間の間、民に殺されなかった囚人はいったん牢に戻し、のちにあらためて磔にして殺した。
しかし竹鋸によるこの首挽き惨殺刑は、江戸期も、キリシタンという重罪人に対しては実際に行われることがあった。
明治期の刑罰
明治維新から王政復古という時代に入り、天皇勢力が再び歴史の表舞台に登場したが、この時、死刑を廃した平安の刑法復活とはならず、江戸の刑法改正は、慎重に見送られた。この政権交代は、明日に迫った国家間戦争に対処するための緊急交代劇という性格が強かったから、威圧の手綱を緩めることは禁物であり、ある部分ではむしろ強める必要があった。
王政復古の体裁をとるため、この刑法は骨子を「大宝律令」時代の「苔・杖・徒・流・死(ち・じょう・ず・る・し)」とする必要があったが、苔と杖とは同じ鞭打ちの意なので、明治政府は「苔・徒・流・死」とした刑法「新律綱領」を、明治三年(一八七○年)に交付している。
しかしこの時点では大宝律令復興は掛け声ばかりで、「磔」、「獄門」、「死罪」、「切腹刑」は依然残され、現状維持だった。廃止されたものは、もともと用をなしていなかった「鋸挽き」と、「火罪」だけである。明治元年には新選組の近藤勇が、斬首刑に処せられている。
明治五年になって、ようやく「鞭打ち」の刑が廃止され、「懲役刑」が設けられた。死刑の方法は、大宝律令の持っていた死刑、「絞」と「斬」から、絞首刑が採用された。当時の絞首刑は、囚人を絞首して、柱に吊すという方式であった。
しかしこの方法では失敗も出た。明治五年十一月二十八日に死刑を執行された田中藤作という人物の遺体が、執行後遺族に下げ渡され、遺族が担いで家に戻る途中で蘇生した。進退伺いを出したが、すでに刑を受けたものと見なされ、無罪放免された。
翌六年(一八七三年)には「徒」と「流」が廃止され、すべて懲役に変える「改定律例」が交付され、「鞭打ち」の刑罰は正式に廃止された。
太政官布告第六十五号によって、当時欧州で行われていた死刑装置「ガロッテ」の模倣が宣言された。これは死刑のたび、木で台と枠組み、階段などを新調し、両手を背後で縛った囚人に紙で目隠しをして階段を上がらせ、上に用意した綱の輪に首を入れさせてから、囚人の立つ床を落として絞首するという方法である。階段は十七段と正式に規定され、この装置は大正年間まで用いられた。
現在の死刑装置も、基本的にはこれを踏襲している。死刑囚に高い階段を上がらせるのは気の毒であり、時に手こずるので、綱の下まで床続きとし、そこから地下に落下させる方式を取っている。ただし、この変遷は自然に見えても、地下絞架式に変更すると謳った法規は、いかなるものにも見い出せない。
明治十三年(一八八○年)には「旧刑法」が制定され、内容が漸次良識的に緩和されて現在に至る。
■現在の死刑
現在の刑法典から、死刑関連の条文を拾いあげてみる。
刑法 第十一条
①死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
②死刑の言い渡を受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
刑事訴訟法 第四七五条(死刑の執行)
①死刑の執行は、法務大臣の命令による。
②前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願、若しくは申出がされ、その手続きが終了するまでの期間、及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に参入しない。
第四七六条(同前)
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。
第四七七条(同前)
①死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長、又はその代表者の立会いの上、これを執行しなければならない。
②検察官、又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
第四七八条(同前)
死刑の執行に立ち会った検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長、又は差の代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
第四七九条(死刑執行の停止)
①死刑の言渡しを受けたる者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。
②死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。
③前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後、又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
④第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日、又は出産の日と読み替えるものとする。
判例、死刑確定者の拘置の停止
死刑の言渡しを受けた者が心神喪失の状態になっても、法務大臣の命令によって停止されるのは死刑執行自体であり、監獄における拘置を解かれるものではない。 (東京地決昭和62.4.23判時一二二九・一〇八〈帝銀事件第二次人身保護請求事件〉)
刑事施設に於ける刑事被告人の収容等に関する法律
第二条(警察留置場)
警察官署に付属する留置場は之を刑事施設に代理することを得。但懲役又は禁固に処せられたる者を一月以上継続して拘置することを得ず。
第七一条(死刑)
①死刑の執行は刑事施設内の刑場に於いて之を為す。
②大祝祭日、一月一日二日及び十二月三十一日には死刑を執行せず。
第七二条(解縄)
死刑を執行するときは絞首の後死相を検しなほ五分間を経るに非ざれば絞縄を解くことを得ず。
天皇の御世となった際、死刑のない平安の法体系に戻れる好機ではあったが、当時は迫り来る国家間殺戮戦の前夜にあたり、国民皆兵の国策のため、死刑を廃止することなど、夢想も許されなかった。
続いて戦後、敵国兵への死刑判決であるところの宣戦布告を成す権限を、日本国家が放棄したことによって、死刑もまた放棄される流れにあったが、続く冷戦の時代を見据えた米軍が、米国にとっては堤防である日本列島に、赤軍兵士のための死刑を残す必要があって、この時も廃止は見送られた。
そして浅間山荘赤軍兵の処刑により、日本の死刑制度は終焉を迎えるはずであったが、今度は軍国日本の亡霊のようなオウム死刑真理教が現れ、わが死刑は、いまだその使命を終えられないでいるらしい。
現在の日本の死刑は、検非違使台頭から江戸期、明治期にかけて続いた死刑信奉を、その核の部分に抱き続けている。しかし性器の切断や縫合、鼻そぎや耳そぎをなくした江戸期、さらに鞭打ちや入れ墨、獄門や切腹をなくした明治期を経ながら、最も残虐な死刑のみは無理に残しているがため、現在の法体系中の死刑は、まるで透明人間のように空虚であり、異質である。
江戸期の死刑は、素朴ながら囚人や民に対し、罪の償いとしての構造を明瞭に説諭していた。放火犯には焼殺、より重罪の者には引き廻し、鋸引き、さらには獄門、晒し首の罰を付加した。これらは労役によっても、死ぬことによっても天秤が吊り合わない重罪者への、追加の分銅である。
当時は、死刑の下に、懲役刑はむろんのこと、鞭打ち、入れ墨刑、流罪、財産没収も、奴隷の刑もあった。これらはすべて、罪の償いとしての反省を、強権をもって罪人に強いる性格のものであり、これらでは相殺しきれない重罪者であるから死罪があるのだといった階級構造を、民に知らしめていた。
さらにその死罪も、死だけでは償えない重罪の者は、死の苦痛や恥を大勢の大衆に見物されることで、為した重罪に相応の贖いがもくろまれた。また死後は、その遺体をもって刀剣の切れ味を確認させることによっても、罪を償わされた。仲間の受けるこれら仕置きを牢内で知ることにより、この法の威圧の精神を罪人は学び、行刑側が面子と秩序維持の狂人であることを心得た。
ところが今日の刑罰は、人権配慮や情操教育という良識ゆえに、鞭打ちや入れ墨、奴隷刑といった残虐刑をすべて廃し、そのため、財産刑である罰金刑と懲役刑、あとはもう死刑しかなくなって、死刑囚に対しては、いっさいの反省要求が消えた。残虐を嫌いながら、殺人の残虐だけを無理に残した論理矛盾のゆえである。良識的誠実を有する上位人が、いったい何ゆえ同胞を殺害するのか。被告は何故死ななくてはならないのかが、これらの法文からは不明である。日本の刑罰とは伝統的に殺害だったのであるから、前例遵守は自明である、という以外の理由が見当たらない。
今日、人権と情操に配慮して処刑は秘密裏に行われた上、遺体も厳重に民の目からは隠蔽される。これでは当然ながら犯罪への威嚇とはならず、宅間守事件のように、弱者連続殺人の誘導さえ成す。そしてこの異様な臆病は、死刑囚に袋貼りひとつ要求せず、改悛の情も求めず、ただ死ぬことだけを「懇願する」という珍妙な結果になった。理由説明がないこれでは、法としての体裁を成していない。いつの時代も、法とは自信に充ちて罪人に償いを要求し、その理由を説諭し、上位者として最大効率的に秩序回復をはかろうとするものであるからだ。
ここにあるものは、長く発狂的威圧によって民を怯えさせ、成していた秩序構造への洞察から、これを緩めれば自身が報復されるという上位者の怯えと見える。しかも自身が責任を取りたくないため、死刑囚には猛反省の上で自殺をしてもらい、行刑はこれを手伝うのみという体裁にしてある。憲法違反の残虐刑との批判が相次いでも、薬殺、斬首、電気ショックを採らず、絞首にこだわるのは、この方法が最も多く自殺に用いられるがためと考えられる。
封建時代、また戦時、死刑はそれなりに合理的であり得たが、殺戮の必要が消えた現在、罪人の鞭打ちを放棄した良識的国家による殺人の宣言は、亡霊のようにぽつんと宙に浮いて、良識的国民感情に対して異様なまでに有害である。対象への罰則行使という自己暗示を成さずに犯罪を為した被告を、筆者は知らない。死刑は、犯罪体質の者に傲慢と自己正当化の方便を教育し続けており、さながら法体系という人体に取り付いた厄介な腫れ物のようで、しかるべき手当てののちに切除しても、この文章ならば何の不都合も出ない。
江戸の頃、死刑囚は日本橋の雑踏に晒されることで罪を償わされた。人権に配慮し、国民の目から隠蔽された今日の死刑囚は、すべからく未決囚となる。法は死ぬことのみを要求しているのだから、生きている限り、いかに反省しようとも、労働奉仕に精を出し、世間に貢献しようとも、彼はかけらも罪を償ってはいない。絞首台に乗り、足下の床板が落ち、空中にぶら下がった瞬間に彼は囚人に戻り、数秒ののちに死者となって罪を償う。
死だけを命じられ、晒しも懲役も課せられていなければ、絞首台の落下板に足を載せるまでは、彼はわれわれ同様一般人である。刑死の義務以外においては、彼はわれわれと同じく社会で映画を観、旅行をし、家庭を営み、刑死の順番が来たなら粛々と刑場におもむけばそれでこと足りる。このような珍妙な要求をする法は、福祉の一環足りえない。
しかるのち、落下した彼に起こる現象は「縊死」であり、法が定めて言う「絞首」ではない。
刑死した遺体は無残に破壊され、刑務官の誰もが正視できず、清掃や納棺の仕事を嫌う。これが、憲法に違反する「残虐な刑罰」であるがゆえであることは、子供にでも解る理屈である。
さらには、確定から六箇月以内に執行された死刑囚を、筆者はここ当分見たことがない。死刑は鋸引きの罪人が晒し刑同等となった江戸期の例と同じく、今日では限りなく「終身刑」に近い。
死刑に関する限り、このように今日の法はあらゆる面で空文化しており、嘘をつき続けており、すでに運用の無理を露呈している。
島田 荘司(しまだ・そうじ)さんのプロフィール
1948年、広島県生まれ。武蔵野美術大学卒。'81年に刊行された『占星術殺人事件』で本格ミステリー復興の旗手となる。常にミステリー界の最前線を走り続け、御手洗潔、吉敷竹史の両シリーズは圧倒的な人気を誇る。また、近年は、「冤罪事件」や「死刑問題」に象徴される日本人論などの社会的な発言や著作でも注目を集めている。近著に、『吉敷竹史の肖像』、『龍臥亭幻想』、『摩天楼の怪人』などがある。