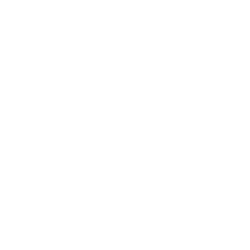死ぬるため生くる我が独房
もはや旧聞だが、白昼、小学校に男が侵入し、包丁で児童、教師など二三人を殺傷 した事件は、学校の警備強化、精神障害者にたいする「保安処分」の実施など、世論を一挙に凍りつかせる深刻な一撃だった。
この事件が突き刺した、もうひとつの社会の暗部は、死刑制度である。逮捕直後 、容疑者が犯行の動機として語った、「エリート校の子どもを殺せば、確実に死刑になれると思った」との供述は、想像に絶するものだった。事件すぐあと、各紙とも大きく報道したが、その後、本人は否定した、ともつたえられ、いまだ真偽は定かではない。しかし、「死にたいと思ったが、なかなか死ねなかったから」と動機を補強する言葉もつたえられているので、あながち、警察の一方的な発表として退けることはできない。
自殺する勇気はない。だから、処刑してくれ、ともっとも弱い小学生を刺し殺す行為を前にして、「正常」さを疑わざるをえない。他人をまき添えにしてしか、自分を表現できないのは、極端な甘えである。しかし、容疑者の供述が事実だったと すると、死刑廃止国には、けっして発生しなかった犯罪だったことがわかる。
死刑制度は、その制度のもとに暮らしているひとたちに、死刑への依存という倒錯した心理をもらす。死刑は犯罪をおこなわんとするものへの威嚇装置(抑止力) として存置されている。しかし、予防は完璧におこなわれず、結果にしか適用でき ない。国民へのみせしめとして、犯罪のあとにしか効力を発揮できない。
たとえていえば、犯罪を犯すおそれのあるものを全員逮捕(予防検束、保安処分 )しないかぎり、死刑制度は有効に機能しない。が、殺人は激高した瞬間におこなわれたり、きわめて周到な準備のもとに、完全犯罪を目指しておこなわれるのが通常だから、威嚇の網の目からはこぼれ落ちてしまう。
しかし、それは制度としてあるのだから、死刑存置国の住民は、悪いことをすると死刑、という約束のもとに生活している。その規則を積極的に逆用したのが、こんどの事件の容疑者である。この機能をこれほどまでに単純化してみせつけられる と、残虐な犯罪がつくりだす装置に逆転するこの制度の欠陥に気づかされるのである。
死刑制度をささえる言語は、「潔く」と「男らしく」である。
悪いことをしたなら潔く死ね、男らしく責任をとれ、死んでお詫びをしろ。武士道の精神のようで、卑怯未練に生き延びることは拒絶されている。ごくたまに、政治家や経営者が、そのモラルに従って自殺すると、世間は納得したりする。処刑されるよりも、自殺に同情があつまるのは、民衆のこころの奥底に死刑の残虐さへの忌避があるからのようだ。今回の容疑者のように、自分の生命の始末を、国家の手に委ねようとしたのは、いちじるしい依存といえる。威嚇と依存によって維持されるのは、民主主義国家とはいえない。
あるとき、死刑存廃についての討論会に出席したことがある。
存置論者のひとりである犯罪心理学者が、「自分の娘をまもるために、死刑制度は 必要だ」 と叫んで、喝采をえたことがある。「抑止力」のもっとも感情的な表現だ が、この制度の存廃をめぐる討論で、感情が増幅させられるかぎり、廃止論が説得 性をもつことはできない。存置論者は被害者の感情に忠実であることを根拠にするのにたいして、廃止論者は冷静さを主張するしかないからである。
わたしが死刑制度に疑問をもったのは、冤罪の死刑囚の本『死刑台からの生還』 を書くようになってからである。そのまえに、殺人罪で無期懲役にされていた那須 隆さんのこと(『弘前大学教授夫人殺人事件』)を書いていたことがあった。この事件は、真犯人が名乗りをあげて再審がはじまり、無罪判決となった事件だった。 そのあと、まだ弁護士がたったひとりで、無実を訴えていた『財田川事件』にかか わることになった。
この冤罪事件は、矢野伊吉弁護士の『財田川暗黒裁判』が出版されて着目される ようになり、ついに死刑確定囚だった谷口繁義さんが、三二年ぶりに釈放されるこ とになった。
八○年代には、四人の死刑確定囚の冤罪がたてつづけに晴らされ、釈放された。
死ぬるため生くる我が独房に
奇もなく衒いもなく日続きぬ (佐藤誠)
死刑執行をまつだけの確定囚にさえ、冤罪があるということは、いかに死刑制度 がふたしかな世界に依拠しているかをしめしている。しかし、誤判があるから死刑 制度に反対、との意見にとどまっているのは、どこか落ちつかなかった。
たしかに、人間がひとを裁くかぎり、誤判がないことなどありえない。といって 、もしも、一件の冤罪もないとしたなら、死刑があってもいい、といい切れるのだ ろうか。としたなら、すべての死刑囚をみすててしまう、という問題に直面したの である。
新聞やテレビで「凶悪犯罪」が報じられると、
「親の顔がみたい」
「悪いことをしたなら、自決しろ」
「やっつけろ」
との感情をむきだしにした声がとりあげられる。
「被害者の感情をどうするんだ」
「お前が被害者だったら、そんなきれいごとをいえるか」
そればかりならまだしも、「無期懲役」の判決がでると、「死刑にしてほしかっ た」との遺族の悲痛な声がつたえられる。そういわせられている遺族の姿がことさ ら悲しい。眼には眼を、憎悪の悪循環である。マスコミはその憎悪を商品化してい る。悲しみに沈み遺族の想いが、はたして、人間としての極限の表現が、「殺せ」 の二文字に集約できるのであろうか。殺してはたして、気持ちが浄化できるもので あろうか。
息子を殺され、苦悩のすえ「死刑廃止運動」にたちあがったアメリカの女性が、 死刑執行によって、息子の記憶を汚したくない、というのを聞いて、考えさせられ るようになった。
だれも被害者の遺族に、「殺せ」という感情を捨てろ、ということはできない。 しかし、死刑制度があるからこそ、遺族は極刑としての「死刑」をもとめる。もしも、死刑制度がなくなったら、それ以外の極刑をもとめることであろう。
死刑制度があるかぎり、世に「殺せ」との殺伐とした声がわき起こる。この制度 のパラドックスは、ひとを殺してはいけない、という国家が、命令によってひとを 殺すことにある。憎悪の感情によって、死刑制度が維持され、その制度によって憎 悪の感情が維持されている。きわめて古い国家像である。 悪人は抹殺せよ、裁判はその合法的な手段にすぎない。
中国では年間,数千人が処刑されている。それでも犯罪が減ったとはきいていな い。アメリカには、三七○○人の死刑確定囚がいる。やはり、犯罪が減ったとはき いていない。日本は九三年三月、「法の秩序と正義の維持」を理由に、それまで三 年四ヶ月停止していた死刑が再開され、年に五、六人が処刑されている。それでも 、凶悪犯罪は減っていない。つまり、「抑止力」は、フィクションでしかない。
あとは遺族の感情をどう解決するか、の問題である。被害者補償と終身刑の導入 がひとつの方法になる。それでも、恩赦と釈放の可能性はありうる。ひとに苦痛を あたえつづけることによって、秩序と正義をたもつ、というのは、恐怖政治の一種 でしかない。
日本の死刑は絞首刑である。より人道的な処刑というのは、形容矛盾だが、なかでも絞首刑はもっとも残虐な刑罰である。空中にぶら下がって、悶絶するまで、七分から十五分意識が残っている。
死刑確定囚は、刑場へ迎えにくる係官の足音が、自分の扉の前で止まらないかどうか、聞き耳をたてている、という。一日、一日、小刻みにされた生とは、想像するだけでもたまらない。日本の死刑確定囚は、いま、五六人である。
先進国で死刑制度を存置しているのは、日本とアメリカだけである。全米五○州 のうち、十二州が廃止している。この野蛮な制度を廃止した国は、七五ヶ国、十年 以上執行していないのが、二十ヶ国、通常犯罪だけでも廃止したのが、一四ヶ国、 合計一○九ヶ国であり、これにたいして、死刑存置国は、八六ヶ国である。
日本は一刻もはやく、死刑制度を廃絶して、文明国の仲間いりをしてほしい。政治家とジャーナリストたちの意識の変革と行動が問われている。
(「本」2001年9月号講談社より、文中の数字は2001年11月末現在)
鎌田 慧(かまた・さとし)さんのプロフィール
1938年青森県弘前市生まれ。弘前高校卒。早稲田大学文学部卒。新聞、雑誌記者をへてフリーに。著作:「自動車絶望工場」「ぼくが世の中に学んだこと」「反骨-鈴木東民の生涯」(1990年度新田次郎賞)「六ヶ所村の記録」(1991年度毎日出版文化賞)「鎌田慧の記録」(全6巻、岩波書店)「大杉栄-自由への疾走-」「生きるための101冊」「ドキュメント賭場」(以上、岩波書店) 「家族が自殺に追い込まれるとき」(講談社)「日本列島を往くⅠ・Ⅱ」「怒りの臨界」「いま、非情の町で」(以上、岩波書店)「津軽・斜陽の家」(祥伝社)「いま、この地に生きる」(岩波書店) 「自立する家族」(淡交社)「忘れてはいけないことがある」(ダイヤモンド社)「原発列島を行く」(集英社)「人権読本」(岩波書店)その他多数