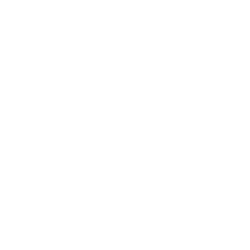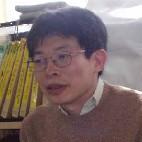
劇作家として、死刑廃止運動について
劇作家という想像力を使う職業柄、死刑について廃止する、しないという単純な問題としてとらえるのではなく、殺された側の論理、被害者側の論理にも想像力を持ちます。このことは決して、廃止運動にとっても無駄なことではないと思います。
そして、死刑廃止運動が、なかなか日本で広がっていかないという理由がもしあるとすれば、そこのところの説得力が少し弱いのではないかと考えています。
これは別に、アムネスティがいいとか悪いとかではなく、日本の――特に市民運動などで――いいことをやっている人ほど、逆の立場の論理について、なかなかうまく語れないということがあると思うのです。
一方で私たちの仕事は、そういうことも踏まえながら、白か黒かをはっきりさせるのではなく、今最善の道は何かということを考えていくということなのだと思っています。
今、できることは何か
僕は、死刑が今の2004年という時点で、絶対悪だとは言い切れるかどうかということに100パーセントの自信はありません。これはやはり、時代によっても変わってくることだと思います。僕自身は死刑に反対ですが、それに反対しない人はおかしいと言えるほどには、まだ社会は成熟していないだろうと感じます。
それに、実際にはもっとひどい――「もっと」と言うと語弊があるかもしれませんが――戦争などが合法的に行われているわけです。いずれ、あと100年か200年もすれば、戦争はなくなるかもしれません。逆にもっと増えてしまうかもしれませんが。
そういうものは、時代によってすごく変わっていきますね。
たとえば人種差別の問題や、同性愛者に対する取り扱いなど、国によってもまったく違うことですし、それを一律に文化の違いや歴史の違いを無視して、単純に声高に反対とか、賛成とか叫ぶことでは、議論は深まっていかないだろうと思います。その上で、今、私たちができることは何かというふうに考えたほうがいいし、きちんと論点をはっきりさせていくということが必要だと思います。
死刑廃止運動にも、いろんな論点があります。もうとにかく、人を殺すということは絶対的に悪なので、それはどんなことがあってもしてはいけないという考え方。それから、冤罪の可能性が否定できない以上は、死刑はいけない。そして、死刑か無期懲役かで、その落差が大きすぎるのではないかということも今、問題になっています。本来これは別問題だと思っていますが、現実的に廃止運動が力を持つためには、そうした諸制度にも言及していかないといけないと思います。
死刑は相手との関係を閉ざす
僕は大学で教えていますが、学生たちによく考えてもらうのは、もし、自分の父親が人を殺したとすると、殺された相手の家族に対して、どんな態度をとるかということです。これには想像力が必要になってきます。答えは人それぞれ違っていいわけで、常にそういうふうに、人それぞれ、時間に応じて態度を選択し、相手との関係を築いていくということが大事なのです。でも死刑というのは、そういうものを一瞬にして閉ざしてしまいます。これが僕の精神的な部分での死刑に反対する理由かなと、今は思っています。
日本ではなぜ死刑に賛成の人が多いのか?
それは宗教心がないということはあるでしょうね。それは非常に大きいのではないかと思います。もともと宗教心みたいなものが薄いように感じます。
それから歴史的にみても、切腹とか、あだ討ちとか、ある意味、生命を軽んずる歴史性というものがあるかもしれません。死をもって償うというようなイメージ、そういう精神風土みたいなものがあるという事実は認めざるをえない。
ただ、それをどう考えるかというのは別のことです。そして、そういうものは変わっていくものですから、変えていかなくてはいけないことと、残さなければいけないことをきちんと考えることが、近代人の仕事だと思います。
逆に言うと、死をもって詫びるとか清算するということは、どちらかというと責任をあいまいにするという風土にもつながります。死刑の問題とはちょっと論点がずれますが、そういう精神風土は、僕はいいと思っていません。なぜなら、システムの欠陥などが発見しにくくなってしまい、社会の向上につながらず、いつまでも同じことを繰り返していくからです。
死刑に犯罪抑止力はない
死刑に犯罪抑止力はないでしょうし、ますますなくなるでしょう。
犯罪の理由がものすごく多様化していきますし、衝動的で、精神の暗闇の部分に結びついている犯罪が増えてきています。そういう犯罪者は、死はあんまり怖くないと思うのです。 もしかすると――人によりますが――自由を抑圧されるほうが、彼らにとっては恐怖であって、終身刑より死んだほうが楽になると考える人がたくさんいるのではないでしょうか。そういう人たちに関しては、決して抑止力になっていないと思います。
犯罪者に同情するわけではありませんが、罪を犯す側にも、何かのつらさとか、痛みがあって犯罪に走るわけですから、抑止力にはならない。ますますならないと言っていくべきでしょう。
被害者遺族の感情
被害者遺族の感情という問題がいちばん大きいと思いますが、一応私たちは、近代社会で個人的な報復はしないということをルールとして定めて、それを法律に委ねたわけです。 その場合に、加害者に対して死んでほしいという気持ちを抱くことと、実際に殺すことの間には、やはり隔たりがあると考えるべきなのです。
死んでほしいと思う人はいるでしょう。しかしそのことと、実際に殺すということには大きな隔たりがあって、その隔たりを無視して、一律に国家が、殺人という報復を請け負うことが、正しいかどうかと考えるべきだと思います。
逆に言うと、加害者と被害者がいて、殺していいですよと判決を下して、ナイフが置いてあったとき、被害者が加害者を殺すかといったら――殺す人もいるかも知れませんが――まず殺さないのではないでしょうか。
死刑という制度があるから、「殺したい」という気持ちが、「殺す」という行為に直結してしまうのではないかと思うのです。
私たちはふだんから殺したいほど憎らしいやつらはいくらでもいます。しかし私たちは殺さない。殺さない手段をとるわけです。そこのところで、議論を飛躍させてはいけないと思います。
身体性が弱まっている現代人
僕たちは演劇をやっているので、「身体性」ということをよく言います。
「身体性が弱い」「身体性が低くなっている」「これは身体性の強い表現だ」などと使うのですが、それは端的にいうと、「痛みを感じる」とか、「からだの調子が悪くなる」ということです。
現代社会というのは、当然、身体性は弱まる方向にいきます。例えば、歩かなくても、電車に乗って移動できるので足は疲れない。同じ距離を歩いても、昔よりは疲れない。冷房や暖房が効いているから、寒いとか暑いとかをあまり感じない。そういうふうに、感覚は弱まる方向にいきます。
でも、それはとても危険な状態です。民主主義国家が比較的、自分たちから戦争を起こしにくいのは、一般市民のほうが身体性が強いからです。一方、王様というのは、身体性が弱いものです。周りの人が何でもやってくれるわけですから。
ところが、今は情報化社会で、そういった身体性がますます希薄になっています。戦争もテレビの中だけ、ブラウン管の中だけでいいわけですから。そうなると自分が痛いとか、返り血を浴びるとか、そういう感覚がなくなってくる。殺したい気持ちと、実際に殺すという作業の間には、本来はいろんな過程があって、どのぐらいのナイフを選ぶのかとか、どのぐらいの強さで絞めれば人は死ぬのかとか、自分の身体にかかわるいろんな段階があります。
しかし、死刑という制度に変えてしまうと、まったく身体性なしに、国家という機関が、代行して、それを行ってしまうわけです。そこがいちばんの問題だと思います。
教育や地域社会のあり方と連動して
日本が死刑を廃止するということを考えると、現実的には何か非常にはっきりしたきっかけがないと変わっていかないと思います。精神風土みたいなものは、なかなか変わっていきませんから。だからこそ、死刑という制度を変えていくということに意味があるのです。
僕はずっと表現教育にかかわってきました。そのときによく先生方に説明するのは次のようなことです。
今私たちは情報社会、高度消費社会に生きていて、お米の作り方を知らなくてもお米を食べられますし、鶏の絞め方を知らなくても鶏を食べられるわけです。そういう環境の中にあって、子どもたちに人の痛みを知れとか、命の大切さを知れと教科書で教えても、これは無理だと思います。それでは子どもたちがかわいそうです。
こういう社会をつくっておきながら、命の大切さを知れということ自体に無理があるでしょう。そういうものは自分の痛み――例えば、氷をずっと手に乗せておいたら、冷たくて痛くなる、しびれてくるというようなこと――からしか本来はわからないわけです。人間はいろんな動植物を殺して生きているということは、直接的な体験からしか学べないわけです。それを全部奪ってしまって、無菌室のようなところに子どもを閉じ込めておいて、命の大切さを知れというのは、矛盾した行為だと思います。
そのためにはどうしても、子どもたちの発達段階に応じて、孤独とか、寂しさ、また死という今までの学校教育が排除してきた人間のネガティヴな部分、心の闇の部分を垣間見させるような体験をさせていかなければいけないと思います。
それは、かつては学校教育ではなく、地域社会が担っていたことです。お寺や鎮守の森などの怖い空間があって、何か触れてはならないものとか、人間はいつか必ず死ぬとか、努力しても報われないことがあるとか、そういうことを地域社会から徐々に学んできたと思うのです。でも、そういう地域社会がもうなくなっています。だから、子どもたちに表現教育、また農作業体験やボランティア活動などのいろんなメニューを用意して、その中で少しずつ、命の大切さを自分に痛みを伴う形で体験させていくしかないと思います。それはとても時間がかかることですし、具体的な運動と並行して行っていかなければならないことですが、そうやって時間をかけて私たちの身体性を回復していかないと、下からの改革はなかなかできないと思います。
その一方で、死刑制度を変えるという声は常に上げていかなければいけません。それによって何かのきっかけになることもあるでしょう。例えば、明らかな大きな冤罪事件が起こって変わるかもしれないですね。それはとてもいいことだと思います。 そのことと同時に、日本の精神風土や今の情報化社会の問題などを変えていくためには、教育とか地域社会のあり方も、少しずつ変えていかなければいけないのではないかと思います。
演劇の力
今年、桜美林大学の推薦入試の課題図書で選ばれたのが文系の人のための先端科学の本でした。クローン人間の話とか、倫理的な問題が扱われていて、志願者はそれについて作文を書いてくることになっていました。ところが、みんな「クローン人間はいけない」と書いていて――それは非常に立派なのですが――どうも道徳的過ぎて、全部当たり前のようで、つまらなかったですね。
それで僕は実技の課題で、自分のクラスにクローン人間が一人いるということにしました。グループごとに創作をするのですが、そうすると断然答えが違ってきますし、きちんと議論が行われます。クローン人間も、いる以上はそこに人権が生じるわけで、そうすると「クローン人間を作っちゃだめだ」というマニフェストだけでは対応しきれない、人間の問題を深く考えるようになります。おとなは今まで、そういう議論をさせてこなかったのではないでしょうか。学校では答えがひとつであって、「クローン人間は作ってはだめです」というところで終わってしまう。
「クローン人間がいたら、あなたならどうするのか」「あなたが、どうしても子どもを産めない体だったらどうするのか」、そういうことをきちんと議論していくということが芸術の仕事です。その意味で、子どものころから、そういうものに触れさせるということには意味があると思います。
痛みを知るための演劇
痛みを伴って体験するといっても限度がありますが、芸術では少なくとも、痛みをシミュレーションする(想定して実験する)ことはできます。
例えば、僕がよくやるワークショップのひとつに、『ロミオとジュリエット』の台本を使って、現代社会で許されない恋愛を描くというものがあります。それでグループごとに話し合ってもらうのですが、いろんなものが出てきます。ふつうの主婦と女子高生がグループを組んで創作する場合もあるのですが、例えば同性愛はどうかという話になる。ファシリテーター(場面を進める役割)の僕は、「じゃあ、あなたの息子さんが、パートナーですと言って、男性を連れてきたらどうしますか?」と尋ねます。そうすると、「いや、ちょっと、それは困るな」とか。一方で女子高生たちに、「お兄ちゃんがそういう人連れてきたらどう?」と聞くと、「ジャニーズ系のかっこいい人ならいい」とかね、いろんな意見が出るわけです。
このように、私たちはフィクションの世界でシミュレーションすることができます。それはとても大事なことです。しかも、ふだんの生活の中では話さないような人――会社の重役さんと女子高生とか、また議員さんと障害者とか――が対等な立場で、ある問題について話せるのです。それが芸術の力です。そういうことを体験しておくことによって、現実に何か起こったときに、もう少し柔軟で、多様性のある対応ができるようになると思うのですね。白か黒かではない対応が、想像力を持ってできるのです。そういう意味では、演劇の力というのは捨てたものではないですね。
麻原被告の死刑判決は
麻原被告に対する死刑にも基本的には反対です。それは、私たちは死刑を選択しない、国家であろうとも人間を殺す選択はしない、ということを選ばなくてはいけないという時代に来ていると思うからです。
死刑という制度を選択肢からはずした上で、あのような凶悪犯罪――どう考えても許せないような犯罪――に対して、社会がどういうふうに対応していくかという議論をしていかなくてはならないのではないかと思います。
死刑というのは、そのような議論を根こそぎ断ってしまうもので、21世紀を生きる私たちが選択するべきことではないのではないかと思います。
死刑を存置する外国に対してのアプローチ
アプローチはしていくべきでしょうね。ただ、現実的にそれをどう解消してゆくべきなのかということは戦略も戦術も相当考えていかなければならないと思います。それは、やはり、経済の問題が非常に大きいでしょうし、宗教の問題も大きいでしょう。それを踏まえたうえで、個別に、その国で死刑を廃止してもらうには、どうしたらよいかということを考え行動していかなくてはならないと思います。理念は非常に大事だし、ときには現実的な行動が理念をゆるくしてしまうようなことがありますから、気をつけなければならないのですが、理念だけでは社会はやはり変わらない。個別に対応することが重要だと思います。
あとは、やはり行って、直接話すことが重要です。韓国でも、東南アジアでも、中国でもそうですが、戦争責任の問題とか、大事なのは、その人の前で、被害者の前で、被害者遺族の前で、私には責任がない、私は悪くない、という発言ができるのかということです。
もしできるならば、それは、相当感情が磨耗しているということでしょう。
一対一の関係でしゃべるということが大事だと思います。
2004年2月26日インタビュー
於:東京・駒場アゴラ劇場事務所
平田 オリザ(ひらた・おりざ)さんのプロフィール
青年団主宰・劇作家・演出家・駒場アゴラ劇場支配人。
桜美林大学文学部総合ぶんか学科助教授。
1962年東京生まれ。国際基督教大学教養学部卒。
1983年青年団創立。
1995年『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞受賞。