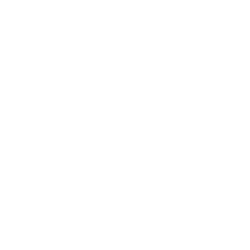---昨年、「スマステーション」(テレビ朝日)で、ダバディーさんが死刑制度について取り上げましたが、その経緯をお聞かせいただけますか?
自分で取り上げたい問題を選んでくださいってプロデューサーに言われたんです。この番組は、硬い新聞を読まないような若い世代に、ニュースもおもしろいですよって、関心を持たせるように作られているんです。
「彼らにはそんなに難しい問題を受け入れる包容力がないかもしれない」と言われましたが、私はそれを作らないといけない、と。
なぜなら、彼らのどこかに知的好奇心があって、受け入れられないはずはないから、彼らの理解力を超える発言になったとしても、ちょっとがんばりたいと思ったんです。
私はもちろん死刑反対ですけれども、それを無理に人に強いることはしません。日本で足りないのはディベートだと思うんです。死刑って何なんですかって。反対・賛成ということの前に、まず、死刑について討論の場を持たないといけないという考え方で。
知識のないところからそういう問題に入ることは非常に難しいから、まず知識を与える。
ですから、番組では廃止している国、廃止していない国の割合を言ったり、死刑の執行方法にどんなものがあるのか――注射だとか電気椅子だとか――という具体的なところまで話したんです。
死刑制度について、ゴールデンタイムのバラエティ番組で話をすることは日本ではとても珍しくて、かなりの反響がありました。日本でいちばん欠けているのは一般知識だと思います。賛成・反対っていう活動に入る前に、まず知ってほしいんです。で、少しずつその人たちが自分で考えればいいなと思ったんです。
---1981年にフランスで死刑が廃止されたとき、今の日本と同じように死刑賛成の人が多かったわけですが、日本でも政治家たちが押し切る形で廃止するべきだと思いますか?
言い方は失礼なんですけども、政治家のような知識人の世論操作があれば圧倒的に反対になると思うんです。死刑という問題はどんな角度から見ても、死刑制度の愚かさは分かるものだからです。
フランスでも、もちろん廃止するでしょってことで、70年代の終わりにアーティストたちが歌を通じて、映画を通じて、新聞の記事または本を通じて、人権の視点から死刑制度の愚かさを一般の人に訴えました。そして一般の人たちがデモをし始めて、ミッテラン大統領のときにバダンテール法務大臣が廃止したのです。
日本でも知識人はマイノリティですから、考えてない人たちを説得するのは大変な時間がかかると思います。そこで、上から一方的に廃止という選択肢もあり得るでしょう。
ただ、そうなったとしても、私みたいな文化人がキャンペーンをやめるべきだとは思わないんです。なぜかというと私は、国家としてその法律がなくなったら嬉しいというのではなく、まさに世論が目を覚ましたら嬉しいから。私の探求は決してこれで終わらないと思います。
---それは今のフランスに対しても同じ?
今のフランスは、世論的には(死刑)反対・賛成が7:3だと思いますが、もちろん賛成の人に会ったときにはディベートもしますよ。
先進国として問題なのはアメリカと日本。もちろんもっとひどいところはあります。独裁主義的な国でしたら、それは独裁主義に反対する理由のひとつになるわけですが、それはまた別の問題で、とりあえず先進国ではアメリカと日本です。
でも、私は日本よりアメリカの方がまだマシだと思うんです。なぜかというと、アメリカはそういう問題について教育された人たちが選んだ道ですよね。彼らがそれなりに自分の考え方を徹底させて出した結論ですから。
日本はディベートまでいってないから、それはいちばん納得いかないところです。ある程度レベルの高いディベートの中で、私の相手が「でも私はやっぱり死刑賛成です」って言ったら、その人の考え方を変えることはしません。ただ、考えてないのがいちばん頭にくるんです。
---日本の法務大臣が「死をもって償うのは日本の文化だ」と発言していますが、それは偏見?
そうですよね。死刑問題を考える角度としては各国の文化、歴史は関係ないと思います。そういうふうに自分の国の文化、背景を踏まえたうえで結論を出すのは一種のナショナリズムだと思うんです。
今の国際社会で求められるのは、国籍、国家、国境は関係ないと理解したうえで、この惑星、地球に生きる人間の人権というか、生きてゆくルールを考えてゆくことですよね。
日本人だろうが、アメリカ人だろうが、フランス人だろうが、人間として考えたところで死刑ってどうなんだろうって。
---被害者遺族への支援を考えるときに、「死刑をなくしてなぜ殺人者だけ生かしておくのか」ってよく言われますが、それについては?
家族の誰かが殺された、きわめて大きなつらさ、寂しさって私は理解するし、同情はできるし、おそらく私も同じことがあれば同じ気持ちになるかもしれません。被害者を心理的にフォローすることは必要です。国によるフォロー、医者や心理学者によるフォロー、もちろん何よりも、友達だとか同じ家族のメンバーによるフォローは必要です。
ただ、厳しい言い方かもしれないですけれども、殺人者って殺された家族の人たちと関係ない人なんですよ。全くリンクされてない。単に自分の息子がその人に殺されたからといって、その人との関係ができちゃったとは思わないです。殺人者と被害者の家族は他人。他人に対する権利はゼロです。
もちろん死刑を考えたときには、両方の立場を考えますよ。でも復讐をする権利はないんですよね。誰にも人を殺す権利はないんです。神にもない。
あとは国の法律があるわけですが、人を殺す権利を保障する法律は成り立たないと思うんです。私は、そこにはディベートの余地はないと思います。
---ダバディーさんはアメリカにも住んでいたそうですが、死刑のない州ですか?
もちろん私は死刑のない州で。
---死刑のないところに住んでいる人にとって、死刑のある国はどのように捉えられていますか?
正直に言うと、「人間の文明が進んでいないところ」って見られているんですね。文明が発展するにつれて、死刑のようなものはなくなるという考え方です。
でも、そういう言い方すると侮辱的だと思うし、そういうふうに私は言いませんが。
---死刑廃止は国際的流れだから、日本も廃止しないといけないと言う人がいますが、それについては?
それは問題を考える角度として間違っていると思います。それはスノビズムであって、私は根本的な問題の真髄を考えてほしいんです。
まず一人一人が最低限の情報、知識を得て、死刑ってどんなものなのか、自分の今住んでいる国でどうなっているのかを知って、個人として意見を出すことです。国として出すのではなくて。
賛成・反対でも、もっと日本でデモが起こったりとか、番組でディベートになったりとか。
「国家として、先進国として廃止すべきかどうか」っていう冷たいディベートではなくて、「人間としてどう思うのか」。人権という角度からのディベートまで進んでいないんですよね。
もしも廃止するとして、単に「ヨーロッパがそうだから」とか「うちもやっぱり先進国だから」ってことでしたら、私は別に廃止しなくてもいいと思うんです。
---日本ではやはりディベートが必要ということですか?
私のメッセージは、まずディベートをして、一般知識として死刑とは何なのかということを知って、そこからどんどん小学校、中学校、高校でも話をしましょうということです。それは大人と話をするんじゃなくて、お互い子ども同士で、大学生同士で。大人でしたら大人同士で話をする。そこから次々と意見、アイディアを出して、それをまとめて考える場所、しゃべる場所を作ることが、日本の場合、いちばん先にくることだと思います。
一般知識が得られたところで、影響のすごく大きなメディアで同じようなディベートを持つ。TVのドキュメンタリーなりトーク番組で、その話題を出す。
第三段階として、世論が成熟したところで政治的なレベルで判断を出すことだと思います。
---ダバディーさんはメディアの世界で仕事をしていらっしゃいますが、死刑に反対する一人として何をしたらいいと思いますか?
まずは「死刑」という言葉を発音して人に知らせること。あまりにも最初からイデオロギー的なことから入るとしたら、それを受け入れる読者とか視聴者は絶対少ないと思いますので。先に一般知識として、いちばん基本的な刺激として話題にすること。
話題にするっていうのは活動だとかキャンペーンではないんですよね。客観的に話題にすることです。それはひとつの役割だと思うんです。
---最後に一言。
「死刑に関する一般知識が足りない」という問題を私はまずクリアしたいんです。だから私は死刑反対派としてどんどん活動することはしませんが、さりげなく一般の人に死刑制度の存在を知らせる人としては知られたいんです。意見を持たない人に刺激を与えたい。意見を持った人を説得することはしません。だけど、一般の人にもっと死刑に関する知識を得てくださいっていうメッセージを私は送りたいと思っています。
(2003年2月17日インタビュー)
フローラン・ダバディー(Florent Dabadie)さんのプロフィール
1974年11月1日フランス、パリ生まれ。父は脚本家ジャン・ルー・ダバディー。母は元雑誌編集長。アメリカUCLAに留学後、パリ東洋学院日本語学科に入学、97年に卒業。98年、映画雑誌『プレミア』の編集者として来日。同時にサッカー日本代表監督の通訳に抜擢されパーソナルアシスタントに。現在は『エル・ジャポン』『エル・オンライン』でライターやパーソナリティ を勤めるほか、俳優、モデルとしても活動中。主な著書は『「タンポポの国」の中の私』(祥伝社)、『モダン・マン~異端に生きる28の法則~』(祥伝社)、『黄金時代』(アシェット婦人画法社)など。